東南アジアのインドシナ半島東岸に位置するベトナムは、第二次大戦後にフランス植民地から独立しますが、社会主義陣営の北ベトナムと資本主義陣営の南ベトナムに分かれます。
その後、南北の対立でベトナム戦争が長く続きましたが、1975年に北ベトナムが勝利して社会主義国として南北が統一されました。
そんなベトナムについて、風土や産業など地理的特徴をまとめていきます。
ベトナムの国土と住民




ベトナムの面積は約33万㎢と日本より少し狭く、インドシナ半島の東岸にS字状の細長い国土が南シナ海に沿って南北に続きます。
北は中国、西はラオス、カンボジアと国境を接しており、北部にはホン川、南部にはメコン川がそれぞれ流れ込み、その下流のデルタ地帯では平野が開けています。
人口は約9600万人と多く、民族的にはベトナム人が多数を占めますが、50を超える少数民族や中国人も居住しています。
ベトナムはモンスーン的風土の気候


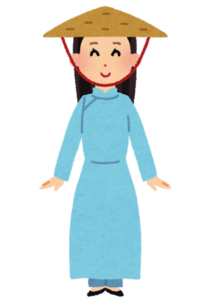
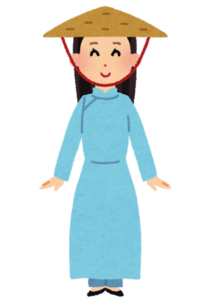
ベトナムの気候は南部が熱帯のサバナ気候であるのに対して、北部は温帯が分布します。
ただ、温帯といっても夏は熱帯と同様に高温で、冬も日本の本州のように寒くならない温暖な気候が特徴で亜熱帯気候と呼ぶにふさわしい気候になっています。
雨季と乾季がはっきりしており、5月から10月に吹く南西からのモンスーン(季節風)が多くの降水量をもたらし、この時期が雨季になります。
11月から3月が乾季で降水量の差が顕著です。このモンスーンによる夏の降水と大きな河川が作り出したデルタの平坦な地形は米の栽培に適した風土です。
この雨季と乾季の季節感はインドや東南アジアのインドシナ半島に共通するモンスーン的風土ということができます。
すなわちインド洋からの夏の南西モンスーンはそれだけ多くの降水量と水の恵みをもたらします。
北部にある首都のハノイと南部の大都市ホーチミンの気候をくらべると、降水量の傾向は似ていますが、気温はかなり差があります。夏の気温は大差がないのですが、冬に差が出るのです。
1月の平均気温が、熱帯のホーチミンでは25.6℃、温帯のハノイで16.0℃と約10℃もちがいます。
メコン川デルタは米の大産地
隣国の中国から流れ込んでくる北部のホン川下流と、インドシナ半島を縦断してベトナム南部へ流れ込んでくるメコン川下流のデルタ地帯では米の栽培がさかんです。
特にメコン川デルタではベトナム全体の約50%の米が生産されます。また、メコン川デルタでは年中高温の気候に恵まれ米の三期作も行われています。
ベトナムの米は世界第5位(2016年)の生産をあげており、2つの川のデルタ地帯では灌漑設備も発達して生産性の高い米づくりが行われています。
輸出も世界第3位(2016年)と米の足りないアジア諸国へ主に輸出されていますが、メコン川デルタが輸出用の米の主産地でホーチミンはその輸出港になっています。
ベトナムは世界第2位のコーヒー生産国
ベトナムはコーヒーの生産が多いことでも知られます。
フランス植民地時代から生産が行われていましたが、1990年代から急激に輸出を伸ばし、現在は生産高、輸出高ともに世界第2位(2016年)を誇っています。
ちなみに1位はブラジルですが、この2国で世界のコーヒーの生産も輸出も50%弱を占めています。
コーヒーの主産地は熱帯気候の南部が中心で、生産されたコーヒーの多くは輸出され、日本も多く輸入しています。
ちなみに、日本のコーヒーの輸入先ではブラジル、コロンビアに次いで3位がベトナムです。
現地ベトナムではベトナムコーヒーという独特の飲み方と味があります。
フランス式の底に小さな穴が開いた金属製のフィルターをカップの上に置きコーヒーを抽出する方法で、抽出に時間がかかるので濃いコーヒーになって苦いため、あらかじめカップの底にコンデンスミルク(練乳)をたっぷり入れておくのです。コーヒーが抽出されるとよくかき混ぜてベトナムコーヒーの出来上がりです。
ドイモイ政策と工業化
社会主義国のベトナムですが、1986年に採択された経済開放政策のドイモイ(刷新)政策により経済が大きく発展しました。コーヒー生産の伸びもこの政策が要因になっています。
中国の経済特区と同じような、優遇税制を実施する輸出加工区もいくつか設置され、日本企業を含む外国企業が多く進出しています。その結果、繊維や機械などの工業を中心に工業化が進み経済発展につながりました。
1995年にはASEAN(東南アジア諸国連合)にも加盟し、現在は貿易額でもASEAN諸国ではシンガポール、タイ、マレーシアに次いで多くなっており、機械類と衣類で輸出額の半分を占めています。
【参考】中国の経済特区ってなに?中学生にもわかるように説明するぞ!
ベトナムの地理要点まとめ
- 日本より少し狭い面積で、インドシナ半島東部を南シナ海に沿って南北に細長い国土が続く。
- 南部は熱帯のサバナ気候、北部は温帯と分かれますが、北部も亜熱帯気候の特徴をもち冬でも温暖。
- 典型的なモンスーン的風土の国で、南西モンスーンの吹く雨季に降水量が多くなる。
- 米の生産と輸出は世界上位で、南部のメコン川デルタで約半分が生産され、ホーチミンから輸出される。
- コーヒーの生産、輸出はともにブラジルに次ぐ世界第2位(2016年)で日本にも多く輸出されている。
- ドイモイ(刷新)政策と呼ばれる経済開放政策で工業生産も大きく伸び、経済発展につながった。
- 【ロシア】要点まとめ!気候、農業、鉱工業について
- 【スペイン】地理の特徴は?気候や家、文化などについて解説!
- 【フランス】地理の特徴は?気候や工業、文化などについて解説!
- 【イギリス】地理の特徴は?経済や産業などについて解説!
- 【ドイツ】地理の特徴は?農業や工業、文化などについて解説!
- 【イタリア】地理の特徴は?気候や農業などについて解説!
- 【韓国】地理の特徴は?気候や自然環境などについて解説!
- 【シンガポール】地理の特徴は?気候や宗教、文化などについて解説!
- 【タイ】地理の特徴は?経済や文化などについて解説!
- 【インド】地理の特徴は?気候や産業、農業などについて解説!
- 【ベトナム】地理の特徴は?気候や農業、風土などについて解説!
- 【カナダ】地理の特徴は?文化、自然、気候などについて解説!
- 【メキシコ】地理の特徴は?気候や宗教、文化などについて解説!
数学が苦手な人には絶対おススメ!
ニガテな数学を基礎から見直しませんか??無料で基礎問題&動画講義をお届け!
今なら高校入試で使える公式集をプレゼント
数スタのメルマガ講座を受講して、一緒に合格を勝ち取りましょう!







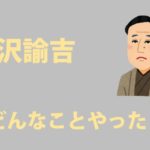

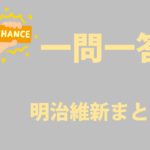
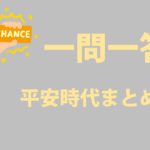
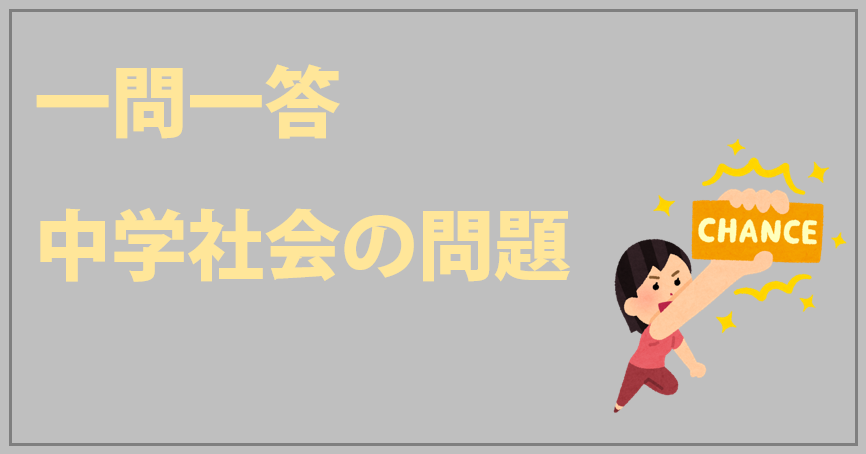
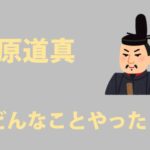
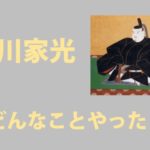



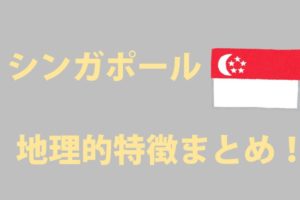




コメントを残す