ヨーロッパの南部、地中海の沿岸には文字通り地中海性気候が分布しています。
今回は、その地中海性気候の特徴
また、その特徴をもたらす理由などを説明していきます。
その後で、地中海性気候が分布する国を押さえて
どのような農業が行われているか、どのような住居の特徴があるか
ということについて学習していきましょう。
ここまでしっかりと押さえると、地中海性気候の特徴は十分に理解したことになります。
地中海性気候ってどんな気候?
地中海性気候の特徴は、夏と冬で大きな差があることです。
夏は雨がほとんど降らず、高温で乾燥します。
そして、草も枯れてしまいます。
草原があるところは茶褐色って感じだね。
夏だけなら、乾燥帯と変わらないような気候になってしまいます。
暑くても乾燥しているから、日本みたいに蒸し暑くはありません。
冬は、ヨーロッパの中でも南部に分布するため温暖で、夏とは逆に雨が降ります。
だから、草原も緑が復活するんだね。
恵みの雨という感じだけれど、降水量が非常に多いということではありません。
それでは、なぜ夏は乾燥して、冬に雨が降るのか?
ということになるんだけれど、
これは次のように考えます。
ヨーロッパの南にはアフリカ大陸があります。
その北部には、年中高気圧に覆われて雨の降らない広大なサハラ砂漠が分布しています。
ヨーロッパの中部は、年中偏西風が吹いて、年中雨のよく降る気候になっています(西岸海洋性気候と言います)。
地中海の沿岸は、ちょうどその間にあるので、気圧配置が移動することによって、
夏はサハラ砂漠を作っている高気圧の、冬は偏西風の影響をそれぞれ受けることになるんだね。
だから、夏と冬で大きな差が出ることになるのです。
というわけで、地中海性気候の特徴は
夏は高温で乾燥、冬は温暖で降雨がある
ということになります。
地中海性気候の国は?
地中海性気候は地中海の沿岸に分布します。




国の名前をあげるとどこだろう?
地中海に突き出しているイタリアがそうだね。
でも、このイタリアに関してはちょっと注意が必要なんだ。
アルプス山脈の麓にあたるイタリアの北部は年中雨の降る気候で、
地中海性気候ではありません。間違えないようにしましょう。
他には、スペインやポルトガル、ギリシャ
そしてもう一つ、フランスの地中海沿岸部も忘れないように!
地中海性気候の国は西から東へ向かって、
ポルトガル、スペイン、フランス地中海沿岸部、イタリア半島部、ギリシャになります。
地中海性気候での農業は?
地中海性気候の地域では、地中海式農業が行われています。
この地中海式農業の特徴3つあります。3つしっかりと覚えよう。
1つ目は、夏の乾燥に強い、オリーブやブドウ、オレンジなどの樹木作物の栽培が多いことです。
これらを主に商品にするんだね。
2つ目は、冬に雨が降るので、小麦を栽培します。
3つ目は、家畜は、やはり乾燥に強い羊の飼育が多いことです。
気候の特徴と関連付けて、しっかりと押さえておこう。
- 夏の乾燥に強い、オリーブやブドウ、オレンジなどの樹木作物の栽培が多い。
- 冬に雨が降るので、小麦を栽培している。
- 家畜は、乾燥に強い羊の飼育が多い。
地中海性気候と住居の関連
地中海性気候の地域の住居の特徴は、石造りの家が多いことです。
地中海やギリシャのエーゲ海の島で、白い石造りの建物が並ぶ風景写真がよく出てくるんだけれど、見たことがあるかな?
地中海沿岸に石造りの家が多いのは、気候と関連しているんだね。
ヨーロッパの住居の材料を調べてみると、
冷涼な気候で雨も降る北部では、針葉樹が多く分布しているので、木造の家が多くなっています。
中部では、木造と石造りの両方がみられます。
そして、夏に乾燥する南部の地中海沿岸は、今では森林がほとんどないので、石造りの家が多くなっています。
というわけで、ヨーロッパの住居の特徴を気候との関連で押さえておこう。
夏に乾燥する気候なので、森林がほとんどなく
石造りの家が多くなっている。
地中海性気候は夏に乾燥する気候
以上、色々な観点から地中海性気候を説明しました。
夏に乾燥するという気候の特徴はもちろん、それが影響する農業や住居の特徴を押さえ、
代表的な国もしっかりと覚えるようにしよう。
数学が苦手な人には絶対おススメ!
ニガテな数学を基礎から見直しませんか??無料で基礎問題&動画講義をお届け!
今なら高校入試で使える公式集をプレゼント
数スタのメルマガ講座を受講して、一緒に合格を勝ち取りましょう!










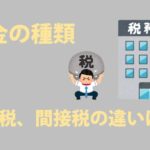
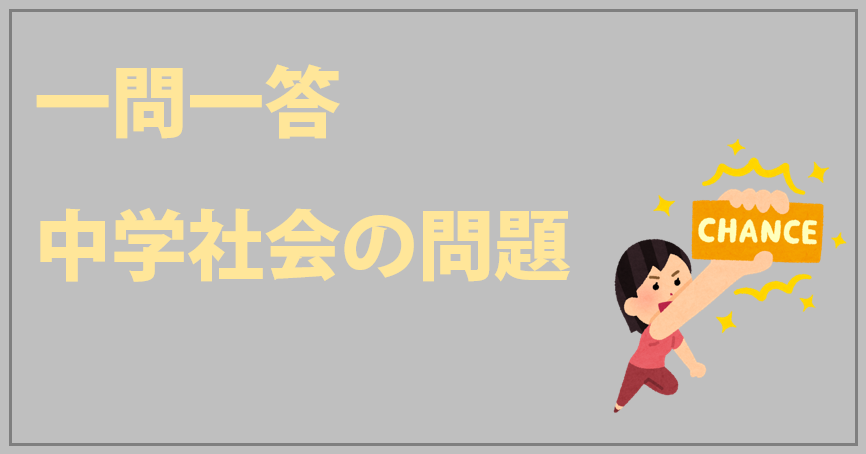









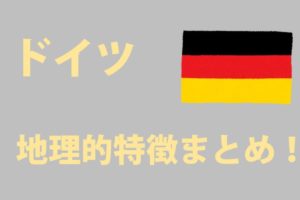
コメントを残す