徳川吉宗の倹約政策によって、なんとかピンチを脱出した江戸幕府。
しかし、またもやテコ入れの時期がやってきた。
そのテコ入れを行ったのが田沼意次(たぬまおきつぐ)だ。
田沼意次は江戸幕府の老中(家臣の中で1番偉い人)で、元々は吉宗の息子で第9代将軍の徳川家重の小姓をしていたんだ。
身分は低かったんだけど、そこからメキメキを頭角を現し、老中まで上り詰めたんだよ。
さあ、そんな田沼意次によって行われた政策をザックリとまとめておくとこんな感じだ。




引用:wikipedia
田沼意次(1719~1788年)
- 第9代・第10代将軍に仕えた江戸幕府の老中
- 株仲間の結成を推奨。
- 印旛沼の開拓を計画するが、失敗。
- 蝦夷地を開発
- わいろが横行し政治が乱れる。
またもや財政ピンチ!商人たちの力を借りよう~株仲間を作れ~
徳川吉宗の時代、米の生産量を増やすことで幕府の財政は持ち直した。
しかし、田沼意次の時にその政策もついに限界になった。
江戸幕府の経済の中心は米。
では、この米中心の経済をやめて貨幣中心の経済にしようではないか。と意次は考えたんだね。
農民へ重税をかすのではなく、経済そのものを発展させて人々の富ませようとしたんだ。
そこで行ったのが、商人たちへの株仲間をつくることを積極的に認めること。
株仲間とは、同業者組合のことだ。
幕府は米だけでなく、商人たちからも貨幣で税金をとりたいと考えていた。
でも、どの時代も税金なんて納めたくないって思うよね。
この時代の商人たちも同じく、税の取り立てにもちろん反抗的。
そこで意次は、株仲間に独占販売権を認めた。
独占販売権を認める代わりに、運上・冥加という営業税を納めるように求めた。
商人たちにとって、独占権はのどから手が出るほどほしいもの。
結果、商人たちは喜んで税金を払い、株仲間に入っていった。
経済も商人中心となり、景気も上向きになったんだよ。
印旛沼を埋め立てろ!~新しい土地の開拓~
吉宗の時代に、印旛沼(千葉県にある湖)を埋め立てることで、田んぼを増やそうという計画があった。
しかし、資金不足と工事が難しかったことにより断念されていたんだ。
そして、時は流れこの計画を引き継いだのが、意次だ。
ただ、意次は新しい新田開発というよりかは、
商業の発展のために利根川を通る船が印旛沼を経由して江戸に行けるような運河を作りたかったみたいなんだけどね。
まあどちらにせよ、田んぼなり、商業施設なり、新しい土地が出来るということは良い事だよね。
が、結果は失敗。
工事の3分の2が終わった時点で、大洪水が起きてしまってたんだ。
その対応に追われているうちに、なんと意次自身が失脚することに…。
この工事はまたもや白紙に戻りました…。
田沼意次失脚!~わいろ政治と天明のききん~




景気が上昇し、経済が安定したことから意次の政治は成功とも思われた。
が、実はその陰に横行したものがあった。
それは、わいろ。
株仲間を奨励したため、商人たちはもっと自分たちを優遇してもらおうとしてなんとわいろを渡しだした。
役人の中にも地位を求めてわいろを贈ったりもらったりと、政治が荒れてしまったんだ。
意次自身にもいくつものわいろが届けられたみたいなんだけど、意次は頑としてこれを受け取らなかったんだ。
にも関わらず、わいろ政治=田沼意次みたいな構図になってしまったのは、意次の政治を快く思っていなかった人たちが、意次失脚の後、人々に植え付けたイメージなんだ。
こんななか、東北地方の冷害から始まった凶作は、浅間山の大噴火も重なり、東北地方の農村を中心になんと数十万の餓死者を出す大被害となってしまった。
このことを天明のききんというよ。
農民たちは生活苦から打ちこわし、一揆をおこすようになる。
意次がその対応に追われる中、嫡男の田沼意知が江戸城内で佐野政言という人物に殺害されるという事件が起こってしまう。
でも、民衆は殺した佐野のほうを「世直し大明神」として称賛したんだ。
民衆は政治や世の中がこんなに荒れてしまったのは、田沼意次の政治のせいだと不満がたまっていたからね。
でも、この意次の嫡男はとっても優秀で、父とともに政治を立て直そうと奮闘していたみたい。
反田沼派に目障りな邪魔者として殺されてしまったんだ。
さらに意次に追い討ちがかかる。
なんと2年後には、最大の後ろ盾である10代将軍が亡くなってしまう。
そしてそのまま意次は失脚。
財産も没収され、城も壊されてしまうんだ。意次は失意のまま死去。
没後、私財も没収されたが、私財という私財はほとんど無かったそうだよ。
わいろ政治=田沼意次みたいに思われているけど、本当はとてもクリーンな人だったんだね。
まとめ!
以上、田沼意次の行った政治についてまとめました。大事なキーワードを下にまとめておきましょう。
- 第9代・第10代将軍に仕えた江戸幕府の老中
- 株仲間の結成を推奨。→商人からも税を。貨幣中心の経済へ変化。
- 印旛沼の開拓を計画→大洪水がおき失敗。
- 蝦夷地を開発
- わいろが横行し政治が乱れる。
- 天明のききんがおき、打ちこわしや一揆が増える。
- 徳川家康の年表、どんな出来事があった?中学生向けに簡単に解説!
- 徳川家光の政策はどんなこと?参勤交代や鎖国について詳しく解説
- 徳川綱吉の政治、やったことは何??
- 徳川吉宗が改革でしたことの内容とは??
- 田沼意次の政策、その目的と結果はどうなった?
- 松平定信の改革、その内容と失敗とは?
- 本居宣長のまとめ!古事記伝の研究とはどんなこと?
- 伊能忠敬まとめ!どんな性格?どんなことをやりとげた人なの?
- 水野忠邦が行った天保の改革とは?
- 杉田玄白まとめ!解体新書とはなに?どんな功績があるの?
- ペリーが来航して何が起きた?結んだ条約は?どこを開港した?
- 井伊直助まとめ!不平等条約からの安政の大獄、桜田門外の変とは?
- 坂本龍馬は何をした人?船中八策とは何?
数学が苦手な人には絶対おススメ!
ニガテな数学を基礎から見直しませんか??無料で基礎問題&動画講義をお届け!
今なら高校入試で使える公式集をプレゼント
数スタのメルマガ講座を受講して、一緒に合格を勝ち取りましょう!





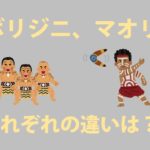
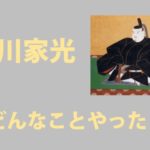
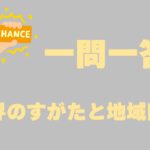

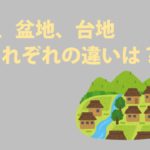

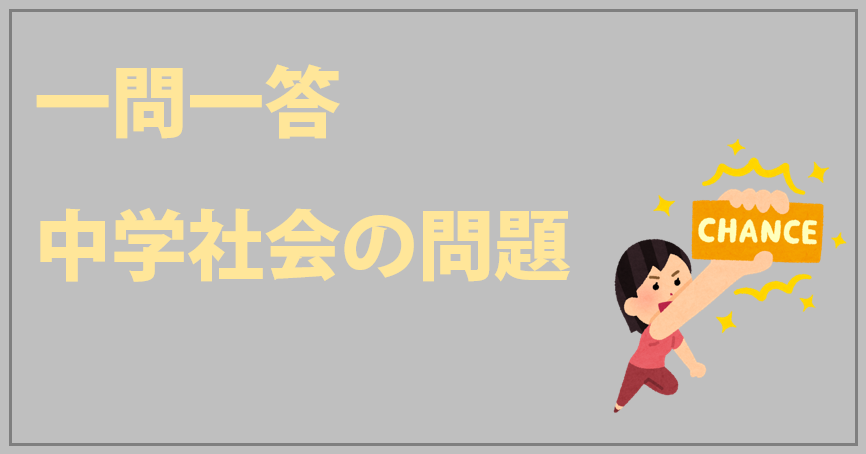
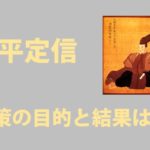
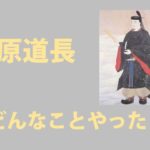
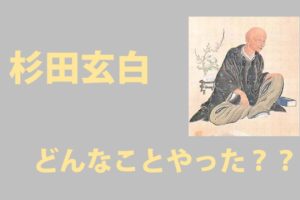
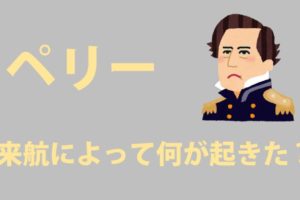
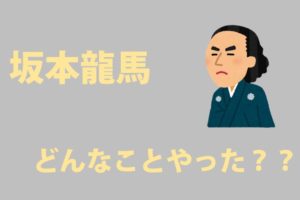
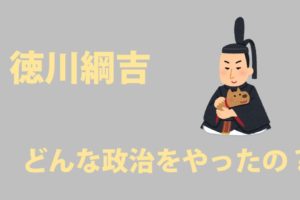

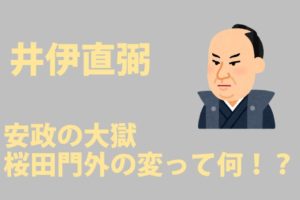
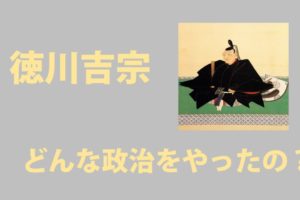
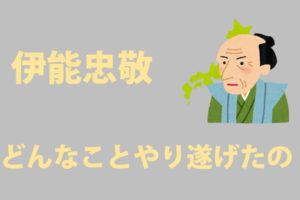
コメントを残す