室町時代の初め、京都と吉野で朝廷が2分した時代があった。
これを「南北朝時代」といったんだけどなぜそんなことが起きたのか。
詳しく解説していくよ。
南北分裂の原因 両統迭立の始まり
遡ること鎌倉時代中期。
当時の治天の君は後嵯峨上皇だった。治天の君とは、実際に権力を握っていた天皇、上皇のことをいう。
後嵯峨上皇は治天の君であり続けるために自分の息子である親王を次々に即位・譲位させ、自分は院政を行っていた。
でも、その体制も崩れてしまう。
後嵯峨上皇が薨去してしまったんだ。
そりゃいくら治天の君でも人間なんだからいずれ寿命は尽きてしまうよね。
ではなぜ後嵯峨上皇の死後、朝廷が混乱してしまったのか。
それは後嵯峨上皇が次の治天の君を指名していなかったからなんだ。
残されたのは2人の息子の後深草上皇(兄)と亀山天皇(弟)。
この2人の間で権力戦争勃発。
収拾がつかなくなり、困った朝廷は幕府に助けを求めた。
当時の幕府は鎌倉幕府。
承久の乱の後、鎌倉幕府に反抗的な天皇は位につけないようにしてたんだけど、今回は別にどちらでも害は無さそう。
幕府としてもそんなめんどくさそうな朝廷の内輪揉めに巻き込まれても…。
困った幕府は2人の生母である大宮院に
「後嵯峨上皇、何か言ってませんでしたか?」とお伺いをたてた。
大宮院は弟の亀山天皇ではないかと答えた。
現に、亀山天皇の皇太子に立っていたのは亀山天皇の息子だ。
後深草天皇にも息子はいたのに、それを差し置いて亀山天皇の息子を皇太子にしたんだ。
これを指示したのは後嵯峨上皇。だから、次の治天の君は亀山天皇というのが後嵯峨上皇も意志だったのではという流れになったんだ。
そうして幕府も治天の君を亀山天皇と認め、無事、亀山天皇は位を皇太子に譲り、上皇となって院政の開始。めでたしめでたし…
とはいかなかったから話はややこしい。
これにものすごく不満を持った人がいる。
そう兄の後深草上皇だ。
もう不満タラタラ。
「上皇」という尊号を突っぱねて強引に出家しようとして幕府に抵抗。
幕府としても後深草上皇がめっちゃ怒るだろうなぁという予想はできてたみたいで、交渉の結果、次の天皇は後深草上皇の息子と決めてしまったんだ。
つまり、こうなる。
後嵯峨上皇
↓
後深草上皇(兄)
↓
亀山天皇(弟)
↓
後宇多天皇(弟の子)
↓
伏見天皇(兄の子)
ややこしいけど大丈夫かな?
で、こうなるとめでたしめでたしとなるといったらそうでもない。
次は誰から不満が出ると思う?
そう、亀山天皇だ。
治天の君となり院政を開始する為には、原則として父→子へと皇位が継承されなければならない。
だから伏見天皇が即位すると自動的に院政は父である後深草上皇が開始することになるのよね。
そして、なんと伏見天皇の後継者として伏見天皇の息子である後伏見天皇が即位することになった。
亀山天皇としたら、自分は父である後嵯峨上皇から正式に認められた治天の君。
それなのにどうして自分の血筋ではなく、後継者として認められなかった兄の息子の血筋が皇位につくのか。
で、幕府に向かってなんとかしろと不満たらたら。
そして、幕府はなんと亀山天皇の血筋と後深草上皇の血筋と交代で皇位につくという案を出してきた。
でも、もう両方の意見を取り入れようと思ったらそれしかないよね。
この朝廷の状態を両統迭立(りょうとうてつりつ)といい、後深草上皇の血筋を持明院統、亀山天皇の血筋を大覚寺統という系統が1代1代交代で皇位につくことになったんだ。
さあ、これで両統とも納得がいくと思うとそうではない。
やっぱり自分の子に皇位を継いでもらいたいと思うのが親心だし、治天の君となって権力を掌握するためにも、できるなら自分の血筋だけで皇位を継承していきたいよね。
仲良く交代で皇位を譲り合っていくというのも無理な話。
様々な小競り合いをしながらも表向きはこの両統迭立で丸く収まったかに見えた。
そう、あの方が天皇の位につくまでは…
後醍醐天皇の即位と両統迭立の崩壊


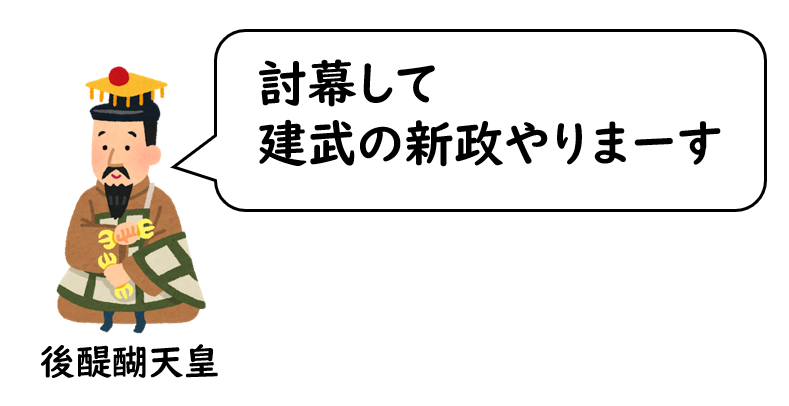
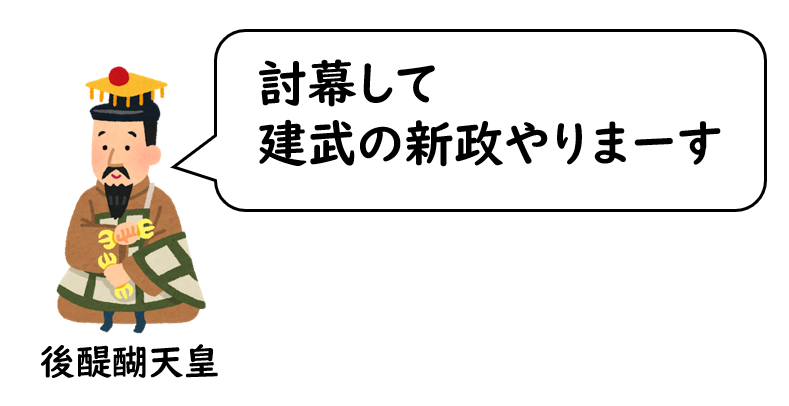
皇位が両統迭立とされてから数十年後。
後に歴史にその名を轟かす人物が皇位についた。
その名も後醍醐天皇。
南北朝時代を作った張本人であるこの御方。
実は後醍醐天皇は中継ぎの天皇だったんだ。
後醍醐天皇は大覚寺統。父である後宇多天皇の遺言によって、兄である後二条天皇の遺児の親王が成人するまでの中継ぎだったんだ。
ちなみに後醍醐天皇までの皇位はこんな感じ。
後嵯峨
↓
後深草(持明院)
↓
亀山(大覚寺)
↓
後宇多(大覚寺)
↓
伏見(持明院)
↓
後伏見(持明院)
↓
後二条(大覚寺)
↓
花園(持明院)
↓
後醍醐(大覚寺)
おおよそ交代でいけてるような。
鎌倉時代の皇位は承久の乱があってから幕府の意志で天皇が決まるようになったんだけど、朝廷で何か問題があるとすぐ幕府へ訴えるようになった。
まあしょうがないっちゃあしょうがないんだけどなんか情けないよね。
そんな情けない状態を何とかしようとしたのがこの後醍醐天皇なんだ。
後醍醐天皇は中継ぎという立場だから当然いずれは皇位を兄の子に渡さなければならなかった。
でも、そんなの嫌だ。
この人は、大覚寺派も持明院派も関係ない。
自分の血筋に皇位を継承したいという野望を持っていた。
父の遺言は鎌倉幕府によって保護されている。
じゃあ、邪魔な鎌倉幕府ごと父の遺言を亡き者としたらいいじゃない!!
こうして後醍醐天皇は自分の血筋が皇位を継承していくために、
討幕を志し2度の失敗にもめげす、見事鎌倉幕府を倒すことに成功。
天皇自ら実権を握り、天皇中心の政治「建武の新政」を開始したのでした。
でも、この政治は大失敗。
内外から不満が続出し、特に武士からの不満はたまる一方。
結局、討幕で後醍醐天皇の右腕となって働いた足利尊氏によって京都を追われ、正統な天皇の証である三種の神器を持って吉野に逃れた。
そこで自分こそは正統な皇位継承者であると主張したものだから事態はまたまたややこしい状態に。
そのころ京都でも足利尊氏に擁立され、持明院派の光明天皇が即位したもんだからさあ大変。
京都と吉野と2つに朝廷が別れた南北朝時代へと突入したのでした。
南北朝時代の終焉と足利義満


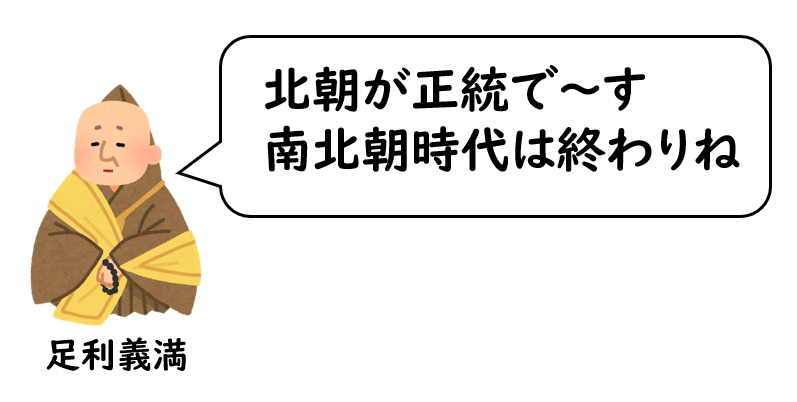
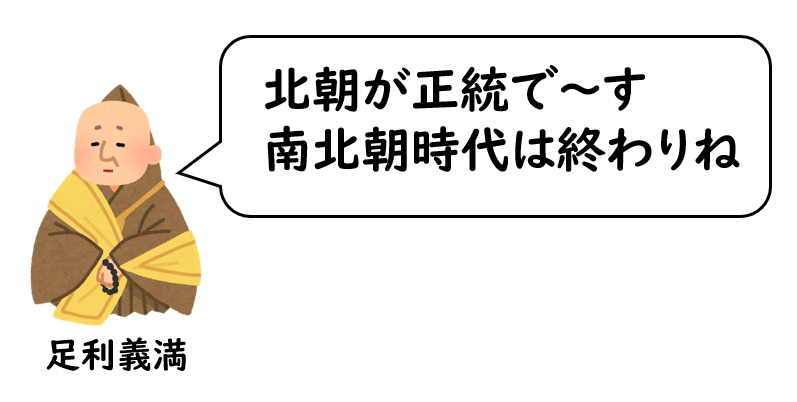
南朝(大覚寺統=後醍醐天皇)、北朝(持明院統=公明天皇)の対立はその発端となった後醍醐天皇の死後にも続いた。
最初は南朝が押していたんだけど、足利幕府が軌道に乗ってくるのに従ってだんだん北朝がその勢力を盛り返してきたんだ。
そうした中、現れたのが3代将軍足利義満だ。
足利義満は吉野の南朝へと和平案を出した。
主な条件は、三種の神器を「国譲り」という形で北朝に返すこと、皇位は北朝と南朝と交互につくこと(=両統迭立の続投)などだ。
内心はどうであれ、双方平等となるように統合しましょうというもの。
後醍醐天皇という良くも悪くも強力な指導者を亡くしていた南朝。
かつてのような勢いはなく、今はもう天皇を凌ぐほどの絶大な権力を握る義満には逆らいたくないっていうのが本音。
表向きは渋々といった感じだけど、内心はどこかホッとした感じで、3種の神器を持って京都に帰って行った。
でもそこは義満。
この3種の神器を南朝から北朝への「国譲り」の儀式ではなく、無くなっていた3種の神器が無事京都へ帰ってきたという意味合いの儀式へと変更して執り行ったんだ。
これはすなわち、南朝の正統性を否定して、北朝こそが正統な皇位継承者であるとアピールするものだったんだ。
元々、足利氏は北朝の天皇から征夷大将軍と任命され、幕府を開くことが許された。
だから、自分達の存在意義のためにも、南朝を正統な皇位と認めるわけにはいかなかったんだよね。
これによって正統性が否定された南朝のメンツ丸つぶれ。
でも、今更義満や北朝と争う力は無く、南朝は北朝へと吸収され南北朝は合一されたんだ。
まあ、何にも不満が出なかったというわけではなく、これ以降もなんやかんやで南朝側が小競り合いを仕掛けてきたりして、結局のところ、応仁の乱が始まってからやっとそんなこと言ってる場合じゃないとかで、この小競り合いが終息に向かったんだ。
な、長い…
ぐだぐだと権力争いが続いたこの南北朝時代。
始まりも終わりもぐだぐだとした感じだったんだね。
南北朝時代のまとめ!
室町時代初期の南北朝時代。
これはそもそも鎌倉時代の大覚寺統と持明院統の争いがもとになり、後醍醐天皇によって京都と吉野に朝廷が分断されたことにより、表面化されていたんだね。
足利義満によって合一されたことはとても重要だからしっかり覚えておこうね。
数学が苦手な人には絶対おススメ!
ニガテな数学を基礎から見直しませんか??無料で基礎問題&動画講義をお届け!
今なら高校入試で使える公式集をプレゼント
数スタのメルマガ講座を受講して、一緒に合格を勝ち取りましょう!





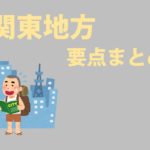


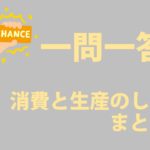


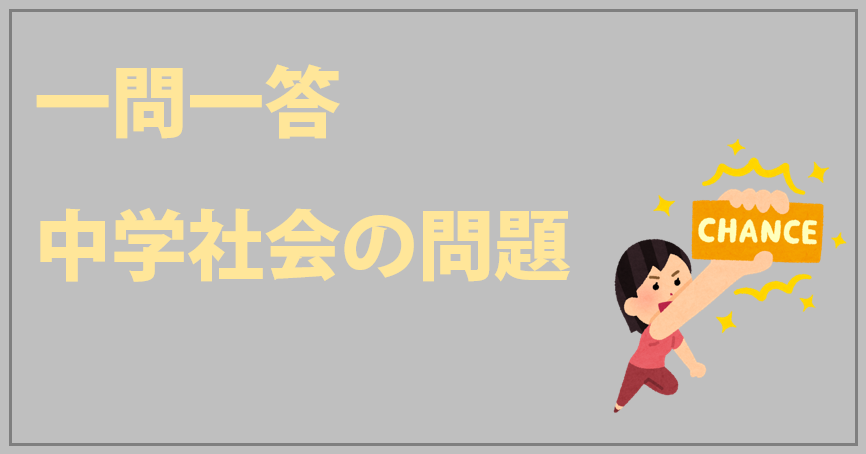





コメントを残す